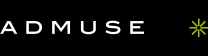- ホーム
- > BtoBサイト制作コラム
- > BtoBサイト制作
- > BtoBサイト構築で失敗しない要件定義の知識と手順
BtoBサイト構築で失敗しない要件定義の知識と手順
Webサイトのリニューアルや新規構築プロジェクト。多くのBtoB企業が、多大な予算と時間を投じたにもかかわらず、
●「蓋を開けてみたら、当初の目的と違うものができあがった」
●「結局、売上やリード獲得に貢献しなかった」
という苦い経験をしています。
特に、製造業やIT企業といったBtoBビジネスのWebサイトは、その構造や目的が一般のBtoCサイトとは大きく異なります。
単なるデザインの刷新ではありません。
●「問い合わせ獲得」
●「リードナーチャリング」
●「営業活動の支援」
●「システム連携」
といった、事業の根幹に関わる目標を達成するためのデジタル基盤、すなわち「仕組み」を構築することが求められます。
その成否を分けるのが、プロジェクトの最重要工程である「要件定義」です。
●「何から手をつけるべきか分からない」
●「社内の意見がまとまらない」
●「外部の制作会社に丸投げして良いのか不安」
といった悩みを抱えるWebサイト担当者、マーケティング担当者、IT部門担当者は少なくありません。
この記事は、製造業およびIT業界に特化しました。
数多くのBtoBサイト構築を支援してきた弊社の専門知識に基づき作成されました。
本記事では、
●BtoBサイトの要件定義を成功させるための知識
●具体的な解決策
そして2025年の最新トレンドに対応した鮮度の高い情報を提供します。
読み終える頃には、曖昧だったプロジェクトの全体像が明確になります。
貴社のビジネス成果に直結するWebサイト構築への道筋が見えるはずです。
目次
失敗を招く要件定義の知識
要点まとめ
BtoBサイトの要件定義は、単なる機能リスト作成ではありません。
事業戦略と直結したゴール設定が重要です。
多くの失敗は
●「目的の曖昧さ」
●「ステークホルダー間の認識のズレ」
●「非機能要件の考慮不足」
という3大要因から発生します。
要件定義の知識を深めましょう。
プロジェクトの土台を固めることが、失敗を防ぐための最初の解決策です。
BtoBサイト構築プロジェクトが失敗に終わる原因のほとんどは、企画段階や要件定義の工程に潜んでいます。
Webサイト構築は、家を建てるのと同じで、土台である要件定義がしっかりしていなければ、いくら立派なデザインを施しても、すぐに問題が発生してしまいます。
BtoBサイト要件定義の特異性
BtoBサイトの要件定義がBtoCサイトと比較して特異なのは、その目的と複雑な構造にあります。
目的が商談と売上直結
BtoCサイトが「購入完了」を最終目的とすることが多いのに対し、BtoBサイトの目的は「問い合わせ」「資料ダウンロード」「デモ依頼」といったリード獲得であり、その最終的なゴールは「商談成立」と「売上」です。そのため、要件定義では、単なる使いやすさだけでなく、リードナーチャリングを意識した導線設計やフォーム機能、MAツールとのシステム連携といった営業活動を支援する機能要件が必須となります。
関与者が多岐にわたる
意思決定に関わるステークホルダーが、経営層、営業部門、マーケティング部門、IT部門、広報部門と多岐にわたり、それぞれの部署の要望を整理し、共通認識を持つための合意形成のプロセスが非常に重要です。この合意形成の知識と手法が不足すると、要件が途中でブレてしまい、プロジェクトが迷走する大きな要因となります。
技術訴求の深さ
製造業やIT企業のBtoBサイトでは、製品やサービスの技術的な詳細や専門性が深く求められます。これをどのようにWeb上で分かりやすく、かつE-E-A-Tに強く訴求するかというコンテンツ要件も、一般的なWebサイト構築よりも複雑になります。
BtoBサイト構築で失敗する3大要因
BtoBサイト構築でよく見られる失敗には、共通したパターンがあります。
1.目的が曖昧なままの進行
「とりあえずデザインを新しくしたい」「競合他社がリニューアルしたから」といった曖昧な動機でプロジェクトが始まり、具体的なKGIやKPIが設定されないまま進行します。結果、制作会社に丸投げとなり、見た目は整っても、ビジネス成果に結びつかないWebサイトが完成してしまいます。
2.ステークホルダー間の認識のズレ
営業は「とにかく問い合わせ数を増やしたい」、ITは「セキュリティと既存システム連携が最優先」、マーケティングは「コンテンツを充実させたい」など、各部門の要望が整理されずに盛り込まれ、サイト全体の方針がブレます。要件定義の段階で、全ての関係者を集めたワークショップを実施し、優先順位と役割を明確に定める解決策が必要です。
3. 非機能要件の考慮不足
サイトの「使いやすさ」や「機能」ばかりに目が行き、裏側の基盤となる「非機能要件」の定義がおろそかになります。特に製造業などの大規模サイトでは、トラフィック増加時の安定性、セキュリティ、MAツールやCRMとのシステム連携、将来的な拡張性といった要素が欠けていると、運用開始後に深刻な問題が発生します。非機能要件の知識と定義は、プロジェクトの安定稼働に不可欠な解決策です。
B担当者が抱える要件定義の悩み
BtoBサイトの要件定義を担当する方が、現場で最も抱えやすい悩みは以下の通りです。
社内調整の難しさ
多くの部署から意見や要望が寄せられ、それらを全て盛り込もうとして、結果的にまとまりのない要件になってしまう。
技術的な知識不足
サーバー、ドメイン、セキュリティ、CMS選定、システム連携といった技術的な専門用語や知識が不足しており、制作会社とのコミュニケーションがスムーズにいかない。
予算と工期の制約
理想的なWebサイトを構築するために必要な工数や予算感がわからず、提案されたスケジュールや費用が妥当なのか判断できない。
これらの悩みを解決するためには、要件定義の工程を体系的に学び、客観的な判断軸を持つことが最も重要な知識となります。
本記事の各ステップが、その解決策を提供します。
要件定義の準備と戦略の知識
要点まとめ
要件定義を成功させるには、まず「なぜリニューアルするのか」という目的を明確にします。
具体的なKGIとKPIを設定することが不可欠です。
また、プロジェクトの成功には、Webサイト担当者だけではありません。
●経営層を含む全ステークホルダーとの合意形成の知識
●プロジェクトチームの明確な体制構築
この2つが求められます。
要件定義書の作成に入る前に、プロジェクトの根幹となる目的と目標、そしてチーム体制を確立しておく必要があります。
この戦略的な準備が、後の工程での手戻りやブレを最小限に抑える解決策となります。
目的と目標の明確化が成功の鍵
Webサイト構築の成功は、この初期段階での目的定義の質によって左右されます。
「なんとなく集客力を高めたい」といった曖昧な目標ではありません。
事業戦略と直結した具体的な目的を明確化します。
事業戦略との一致
Webサイト構築が、企業の経営目標(KGI)の達成にどのように貢献するのかを定義します。「売上を〇〇%向上させるための、優良な商談を〇〇件獲得する」といった上位目標と連携させます。
KGI/KPIの設定
最終的なビジネスゴール(KGI: Key Goal Indicator)と、それを達成するためのWebサイト上の具体的な行動指標(KPI: Key Performance Indicator)を設定します。
KGIの例
顧客単価の高いサービスに関する問い合わせ経由の年間売上を20%向上。
KPIの例
特定の技術資料ダウンロード数を月間100件、リードナーチャリングメールの開封率を30%、商談化率を5%に設定。
ターゲット像の再定義
誰に、何を、どのように伝えたいのかを明確にします。特にBtoBでは、購買に関わる複数のペルソナ(技術者、購買担当者、経営者など)を想定し、それぞれの情報ニーズと行動を把握する知識が求められます。
ステークホルダーと合意形成の知識
BtoBサイト構築では、社内の関係部署が多く、意見の対立や優先順位の齟齬が発生しがちです。
要件定義の段階で、これらの問題を解決するための知識とプロセスが必要です。
1.参加メンバーの選定と役割定義
プロジェクトの意思決定者(経営層)と実務担当者(マーケティング、営業、IT部門)を明確にし、各メンバーの役割を定義します。例えば、マーケティング担当者は「コンテンツ要件」、IT部門は「システム連携・非機能要件」の最終承認権を持つ、といった具体的なルールを設定します。
2.現状分析と課題の共有
GAや既存のデータ分析、営業ヒアリングを通じて、現在のWebサイトが抱える課題(例: 特定の技術記事への流入は多いが、問い合わせに繋がっていない)を客観的な数値で共有します。この共通認識が、新しいWebサイト構築の「必要性」と「方向性」について合意形成するための土台となります。
3.RFP作成による要望の整理
外部の制作会社に依頼する前提であれば、この段階でRFP(提案依頼書)のドラフトを作成します。RFPは、自社の要望や課題、予算、希望納期などを文書に整理する絶好の機会となり、社内の要望の抜け漏れを防ぐ解決策となります。
プロジェクト体制とスケジュールの知識
要件定義の成功には、外部パートナー(制作会社)との連携を含む、円滑なプロジェクト進行の知識が不可欠です。
プロジェクト体制図の作成
社内チームと制作会社チームの責任者、担当者を明確にした体制図を作成し、コミュニケーションの窓口を一本化します。これにより、情報が錯綜するのを防止します。
スケジュール管理の厳守
要件定義フェーズは、後の設計・構築工程に大きな影響を与えるため、期間を明確に定めて厳守します。期間が長引きすぎると、市場や競合の状況が変化し、せっかく定めた要件の鮮度が失われてしまうリスクがあります。
コミュニケーションルールの確立
会議の頻度、議事録の形式、各種ドキュメントの承認フローなど、プロジェクトをスムーズに進めるためのルールを事前に取り決めます。特にBtoBサイト構築においては、システム連携に関わる専門的な内容の確認が増えるため、IT部門との連携頻度を高めに設定することが望ましいです。
必須要件を網羅する解決策
要点まとめ
要件定義書の核心は、機能要件と非機能要件の明確化です。
特にBtoBサイトでは、
●リードナーチャリングに必要なMA連携
●セキュリティ
●拡張性
といった非機能要件の定義が構築の成功を左右します。
また、将来の事業展開を見据えたCMSの選定は、サイト運用コストの増減に直結する重要な解決策であり、この知識は欠かせません。
要件定義の工程で最も時間と労力を要するのが、Webサイトに求められる具体的な機能と性能を定義することです。
ここで抜け漏れがあると、構築後の手戻りや、運用後のトラブルの原因となります。
機能要件の洗い出しと優先順位付け
機能要件とは、Webサイトが持つべき具体的な機能(例: 検索機能、フォーム機能、CMSの管理機能)です。
1.ユーザー視点での機能リストアップ
ユーザー(見込み顧客)がWebサイトを訪問してから問い合わせに至るまでの行動(カスタマージャーニー)をシミュレーションし、それぞれのステップで必要となる機能をリストアップします。
例: 製品比較の段階 $\rightarrow$ 比較表機能、PDF資料のダウンロード機能
例: 問い合わせの段階 $\rightarrow$ 入力フォームのEFO機能(入力補助)、サンクスページでの次のアクション誘導
2.部門別機能の定義
サイト運営者(マーケティング、広報、営業)が使用する裏側の管理機能についても詳細に定義します。
例: CMSのコンテンツ更新の容易性、リード情報のエクスポート機能、ABテスト機能、アクセス解析タグの管理機能
3.優先順位の決定
全ての要望を一度に実現することは予算とスケジュールの制約上困難です。「必須(Must)」「重要(Should)」「希望(Want)」などの軸で優先順位をつけ、フェーズごとの実装計画を立てます。このプロセスで、社内での合意形成を図る知識が役立ちます。
成功を左右する非機能要件の定義
非機能要件とは、Webサイトの機能そのものではありません。
品質や性能、運用に関わる要件です。
BtoBサイト構築において最も見落とされがちな知識領域です。
性能・拡張性
将来的なトラフィック増加や、コンテンツのボリューム増加に耐えうるサーバー性能、システムの拡張性を定義します。例えば、「月間PVが現在の3倍になっても、ページの表示速度は〇〇秒以内を維持すること」といった具体的な数値目標を設定します。
セキュリティ
BtoBサイトは顧客情報や機密性の高い技術情報を扱うため、セキュリティ要件は非常に重要です。SSL/TLSの利用はもちろん、WAF(Web Application Firewall)の導入、ISMS(ISO 27001)などの認証基準への準拠、個人情報保護ポリシーに沿ったデータ管理体制を非機能要件として明記します。
保守・運用
障害発生時の復旧目標時間(RTO)、データのバックアップ頻度、CMSのバージョンアップ対応、Webサイトのメンテナンス体制など、運用後の安定性を保証するための要件を定義します。
システム連携
既存のMA、SFA、CRM、基幹システムとのシステム連携方法(API連携、CSV連携など)と、連携させるデータ項目を詳細に定義します。特に製造業のBtoBにおいては、製品の在庫情報や価格情報との連携も視野に入れる必要があります。この非機能要件が、Webサイトを単なる情報発信ツールではなく、営業活動を支援するプラットフォームに変える鍵となります。
CMSとMAの選定知識と解決策
Webサイトの要件定義において、
●どのCMS(コンテンツ管理システム)を採用するか
●またMA(マーケティングオートメーション)ツールとの連携をどうするか
というCMS選定は、その後の運用効率とリードナーチャリングの成否に直結します。
1.CMS選定の観点
コンテンツ更新の容易性
マーケティング担当者や広報担当者が、専門知識なしで記事やページの更新を簡単に行えるか。
拡張性
将来的に多言語対応やEC機能、会員制機能などを追加する可能性があるか。その際にシステム連携が容易か。
MA連携の親和性
採用予定または既存のMAツール(例: Pardot, Marketo, Hubspot)との連携がスムーズに行えるか。特にリードの行動履歴を細かく取得できる機能が充実しているかが重要です。
2.MA連携の要件
CMS選定と同時に、MAで何をしたいのかを定義します。「資料ダウンロード後の自動メール配信」「特定の技術記事を3回以上閲覧したリードのスコアリング」「営業へのホットリード通知」といったリードナーチャリングのシナリオを想定し、必要なシステム連携の要件を明確にします。
3.内製化と外注の切り分け
CMS選定後、初期構築は制作会社に依頼し、その後のコンテンツ更新や簡単な修正は内製化できるように、CMSの操作トレーニングやマニュアル整備を要件に含めるべきです。
顧客体験を高める設計の知識
要点まとめ
BtoBサイトの要件定義は、顧客の購買行動を深く理解した設計が不可欠です。
ペルソナに基づいたカスタマージャーニーの策定は、コンテンツの構成と導線を最適化する解決策となります。
また、Googleが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した情報構造とデザインは、SEOに強く、信頼性の高いWebサイト構築に直結する知識です。
Webサイトは、企業の一方的な情報発信の場ではありません。
顧客との継続的な接点を持つための「体験」の場です。
要件定義では、この顧客体験(UX: User Experience)をどのように設計するかが成功の鍵となります。
ペルソナとカスタマージャーニーの知識
BtoBサイトの訪問者は、
1.課題認識から情報収集
2.比較検討
そして意思決定に至るまで、複雑で長い購買プロセスをたどります。
複数ペルソナの策定
技術者、購買担当者、経営者など、購買に関わる主要な人物像(ペルソナ)を具体的に策定します。それぞれのペルソナが、どのような課題を持ち、どのような情報を求め、どのような経路(検索、SNS、展示会など)でWebサイトにたどり着くかを明確にします。
カスタマージャーニーマップの作成
各ペルソナが、認知、興味・関心、比較・検討、行動の各段階で、Webサイト上のどのコンテンツ(記事、導入事例、技術資料、料金ページ)に触れるべきかをマッピングします。このカスタマージャーニーの設計が、必要なコンテンツ要件と、それを誘導するための導線設計の基盤となります。
コンテンツ要件の具体化
ジャーニーマップに基づき、各フェーズで不足しているコンテンツ(例: 認知フェーズ向けの業界動向解説記事、比較検討フェーズ向けの競合比較ホワイトペーパー)を具体的なタイトルや構成案として要件定義に盛り込みます。このコンテンツ要件こそが、Webサイトの集客力とリードナーチャリング効果を最大化する解決策です。
情報構造と導線の設計
情報構造(サイトマップ)と導線(ナビゲーション)の設計は、ユーザーが求める情報に迷わずたどり着けるようにするための設計図です。
1.サイトマップの階層構造
BtoBサイトでは、製品・サービス、技術情報、導入事例、企業情報といった主要なカテゴリーが明確に分けられ、論理的かつ階層的なサイトマップを作成します。特に技術訴求が重要な製造業では、技術情報や専門知識を深く分類する階層を設けることが、SEOの専門性評価を高める上で重要です。
2.グローバルナビゲーションの設計
サイトのどこからでも、主要な情報(製品、ソリューション、問い合わせ)にアクセスしやすいグローバルナビゲーションを設計します。ユーザーテストなどを実施し、直感的に操作できるかを確認することも重要です。
3.CTAの最適化
記事の途中、ページの末尾など、顧客の購買意欲が高まるであろう最適なタイミングと場所に、適切なCTA(問い合わせ、資料ダウンロードなど)を配置する要件を定義します。コンテンツの文脈に応じたCTAの設計は、コンバージョン率を向上させるための重要な解決策です。
E-E-A-Tを意識した信頼性設計の知識
Googleの検索品質評価ガイドラインが重視するE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)は、特に専門性の高いBtoB領域のWebサイト構築において、要件定義の段階で組み込むべき重要な知識です。
専門家の明記
記事や技術情報の執筆者・監修者の情報(氏名、役職、専門分野、経歴)を明確に記載する要件を定義します。製造業であれば、現場の技術者や博士号を持つ研究員の顔を出すことが、コンテンツの専門性を高めます。
信頼情報の配置
企業としての信頼性を示す情報(ISO認証、受賞歴、導入実績、セキュリティポリシー)を、サイト全体からアクセスしやすい場所に配置する要件を設定します。
デザインとUI/UX
信頼感のあるWebサイトは、プロフェッショナルなデザインであるだけでなく、動作が安定し、表示速度が速く、スマートフォンなどあらゆるデバイスで問題なく表示されるUI/UXが求められます。レスポンシブデザインの対応、アクセシビリティへの配慮、ページの表示速度の目標値も非機能要件として定義します。
このE-E-A-Tを意識した設計を要件定義に盛り込むことで、Webサイトは検索エンジンからの評価が高まります。
結果として集客力向上という解決策につながります。
最新トレンドと鮮度を活かす策
要点まとめ
2025年、BtoBサイトの要件定義は、最新のデジタル技術とトレンドへの対応が必須です。
特に
●生成AIの活用によるパーソナライズ
●システムのモジュール化(Headless CMSなど)
そしてWebサイトと基幹システムを連携させるDXの視点が、Webサイトの鮮度と競争優位性を保つための重要な解決策となります。
技術革新のスピードが速い現代において、リニューアルしたWebサイトがすぐに時代遅れにならないように、要件定義の段階で最新トレンドを取り込む知識が必要です。
2025年最新トレンドの要件定義への組み込み
以下の最新トレンドを要件定義に組み込むことで、Webサイト構築の鮮度を保ち、将来的な拡張性を確保します。
1.Headless CMSの検討
Webサイトの「コンテンツ管理(CMS)」と「コンテンツ表示(デザイン)」を分離するHeadless CMS(例: Contentful, Sanity)の採用を検討します。これにより、Webサイトだけでなく、アプリやデジタルサイネージなど多様なチャネルにコンテンツを配信でき、将来的なデジタルマーケティングの展開への拡張性が高まります。
2.生成AIによる顧客対応
24時間365日の技術的な問い合わせ対応や、コンテンツの自動要約を担う生成AIチャットボットの導入を要件に加えます。AIの応答精度を高めるために、FAQや技術資料のデータベースとのシステム連携も非機能要件として定義します。
3.超パーソナライズ
MAツールやBIツールと連携し、訪問者の業種、過去の閲覧履歴、ダウンロード資料に基づいて、トップページや製品紹介ページのコンテンツを動的に変化させるパーソナライズ機能の要件を定義します。これは、リードナーチャリングの効率を劇的に向上させる解決策です。
DXとシステム連携の鮮度を保つ解決策
製造業やIT企業にとって、Webサイト構築はDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の一環と捉えるべきです。
Webサイトと基幹システムとのシステム連携は、単なる情報のやり取りではありません。
業務プロセス全体の効率化に繋がります。
SFA/CRM連携の深化
リード情報だけでなく、営業部門がSFA(Sales Force Automation)に入力した商談の進捗や受注確度などのデータをWebサイトのコンテンツ改善にフィードバックする仕組み(双方向のシステム連携)を要件に含めます。これにより、Webサイトのコンテンツの鮮度が保たれ、常に「今売れているサービス」に合わせた情報提供が可能となります。
在庫・価格情報とのリアルタイム連携
特に製造業の場合、Webサイト上で製品の仕様や価格、在庫状況をリアルタイムで表示するための基幹システム(ERPなど)とのシステム連携を非機能要件として定義します。これにより、顧客の利便性が向上し、営業部門への無駄な問い合わせを削減する解決策となります。
データ分析基盤の構築
GA4やGTMなどのアクセス解析ツールだけでなく、MAやSFAのデータ、そして基幹システムの売上データを統合して分析できるBIツールとのシステム連携を要件に含めます。これにより、Webサイトの改善が事業成果にどれだけ貢献しているかを客観的に評価できる知識と仕組みが手に入ります。
RFP作成と制作会社選定の鮮度
要件定義で定めた内容を外部の制作会社に正確に伝えましょう。
適切な提案を引き出すためには、RFP(提案依頼書)の鮮度と質が重要です。
1.RFPへの要件定義の反映
要件定義で明確にしたKGI/KPI、機能要件、非機能要件を、RFPに抜け漏れなく詳細に記載します。特に非機能要件(セキュリティ、システム連携、保守運用)を具体的に書くことで、技術力の高い制作会社からの提案を引き出しやすくなります。
2.技術トレンドへの対応の要求
制作会社に対し、RFPの中で「Headless CMSや生成AIといった2025年の最新トレンド技術を、貴社はどのように提案に盛り込むか」という質問を設けます。これにより、制作会社の技術的な鮮度と解決策の提案力を評価する軸が生まれます。
3.提案時の評価軸の明確化
制作会社の提案を評価する際、単にデザインや見積もりだけでなく、「弊社の技術やビジネスモデルへの理解度」「MAツールとのシステム連携実績」「E-E-A-Tを意識したコンテンツ戦略の提案力」といった、BtoBサイト構築に特化した評価軸を明確にし、事前に伝達します。
RFPは、制作会社選定の公平性を保つだけではありません。
自社の要望を再整理します。
プロジェクト成功への共通認識を築くための重要な文書となります。
IT/製造業のBtoBサイトに強いBtoBサイト制作会社アドミューズはこちら
要件定義を成功させる行動
要点まとめ
要件定義を成功に導くためには、曖昧さを排除します。
文書化を徹底すること、そして何よりもBtoBサイト構築に特化した専門的な知識と豊富な実績を持つパートナーを選定することが最も確実な解決策です。
発注後も、パートナーと一体となってプロジェクトを進める秘訣を知ることが、最終的な成功へと繋がります。
要件定義の工程は、Webサイト構築プロジェクト全体における最も重要な「行動」です。
ここでの行動の質が、後の全工程の質を決定づけます。
要件定義書を完璧にする知識
要件定義書は、社内および制作会社との間で「何を、いつまでに、どのように作るか」を約束する重要な文書です。
1.5W1Hでの明記
機能、非機能問わず、全ての要件を「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」という5W1Hで明確に記載します。特に「なぜその機能が必要なのか(Why)」という目的を明記することで、後の設計や構築段階で本来の目的から逸脱するのを防ぎます。
2.抜け漏れ防止のチェックリスト
機能要件、非機能要件、コンテンツ要件など、各カテゴリで想定される要件をリストアップし、網羅的にチェックする仕組みを設けます。製造業BtoBサイトの場合、「技術資料のバージョン管理」「多言語対応の要件」「既存データベースとのシステム連携項目」などをチェックリストに含める必要があります。
3.承認プロセスの確立
作成された要件定義書は、関係する全てのステークホルダー(特に経営層とIT部門)の承認を得るプロセスを必須とします。承認された要件定義書は、その後の設計・構築フェーズで変更が発生した場合の基準(ベースライン)となり、無秩序な仕様変更を防ぐ解決策となります。
要件定義書のご相談にも対応、BtoBサイト制作会社アドミューズこちら
BtoB特化のパートナー選定秘訣
BtoBサイト構築、特に複雑な技術訴求やシステム連携が求められる製造業やIT企業の場合、一般的なWeb制作会社ではなく、その領域に特化した専門性の高いパートナーを選ぶことが成功への最短距離です。
BtoB特化の実績と知識
提案書の内容が、貴社の製品やサービス、顧客の購買プロセス(カスタマージャーニー)を深く理解しているかを確認します。単なるデザイン実績ではなく、リードナーチャリングやMA、SFAとのシステム連携の実績が豊富かを重視します。
技術力と解決策の提供
提案された技術的な解決策(CMS選定の理由、非機能要件への対応方法、システム連携のアーキテクチャ)が論理的かつ具体的であるかを評価します。特にセキュリティや拡張性といった非機能要件への知見が深いかを確認します。
長期的な運用支援体制
Webサイトは納品後からが本番です。コンテンツの鮮度を保つためのSEO支援、MAツールの運用サポート、効果測定と改善サイクルの支援など、長期的に伴走できる体制と知識があるかを見極めます。
最適なパートナーを選定することは、プロジェクトの質を高めます。
結果として費用対効果を最大化する最も重要な行動となります。
プロジェクト進行の秘訣と成功への行動
要件定義を終え、プロジェクトが構築フェーズに入った後も、成功へ導くためにWebサイト担当者が取るべき行動があります。
コミュニケーションの円滑化
制作会社との定例会議を定期的に設け、進捗状況の共有と問題点の早期解決に努めます。特に、要件定義書に記載された内容に対する解釈のズレを解消するためのコミュニケーションは、建設的なフィードバックとともに頻繁に行うことが重要です。
迅速な意思決定
構築中に発生する未定義の部分や、軽微な仕様変更の要望に対しては、要件定義で定めた優先順位に基づき、担当部署間で迅速に意思決定を行います。意思決定が遅れると、その遅延が後続の工程全体に影響し、納期の遅延や費用増加に直結します。
テストと品質担保への参画
制作会社に任せきりにせず、受け入れテスト(UAT: User Acceptance Test)に積極的に参画します。特に機能要件や非機能要件が定義通りに実現されているか、営業部門やマーケティング部門の実務担当者の視点で確認し、品質を担保します。
これらの行動は、プロジェクトの遅延を防ぎます。
要件定義で目指した「あるべきWebサイト」を確実に実現するための、Web担当者にとっての重要な知識です。
具体的な解決策となります。
よくある質問と解決策
CMSの選定で失敗しないポイントは何ですか
Q. 多くのCMSがあり、どれを選べば良いか迷っています。BtoBサイトのCMS選定で失敗しないためのポイントは何ですか?
A. BtoBサイトにおけるCMS選定は、以下の
の観点で判断することで、失敗を回避し、将来的な拡張性を持った解決策を選択できます。
1.MAツールとのシステム連携親和性
最も重要です。MAツールとシームレスに連携でき、リードのWeb行動データを正確に取得・スコアリングできる仕組み(タグの埋め込み、フォームの連携など)が簡単に実現できるCMSを選びましょう。
2.拡張性とセキュリティのバランス
将来的な多言語対応や会員機能などへの拡張性があるか。同時に、顧客情報を扱うため、セキュリティアップデートや保守体制が確立されているか(オープンソースCMSの場合は、そのコミュニティの活発さや実績)を確認します。非機能要件を満たすために、クラウドベースでセキュリティが強固なCMSも選択肢に入れるべきです。
3.コンテンツ作成の柔軟性とE-E-A-Tへの対応
専門性の高い技術コンテンツを、レイアウトが崩れることなく、かつ技術者や担当者が簡単に更新できる操作性があるかを確認します。特にE-E-A-Tを高めるための著者情報や監修者情報を明確に表示できる機能が用意されているかも重要です。
RFPを作成する際の重要項目は何ですか
Q. 制作会社に依頼するためのRFP(提案依頼書)を作成する際、要件定義書の内容以外で特に重要視すべき項目は何ですか?
A. RFPの質が、制作会社の提案の質を決めます。要件定義書の内容に加え、以下の3つの項目を明確に記載することが重要です。
1.プロジェクトの背景と事業目標(KGI)
なぜリニューアルするのか、最終的にどのようなビジネス成果(売上、商談数など)を期待しているのかを具体的に記載します。これにより、制作会社は単なる制作技術だけでなく、貴社の事業課題を解決するためのマーケティング戦略まで踏み込んだ提案をしてくれます。
2.既存システムの環境とシステム連携の明確化
現在使用しているサーバー、ドメイン、MA、SFA、CRM、基幹システムの種類と、リニューアル後のWebサイトとどのようなデータを、どのようにシステム連携させるかを明記します。これにより、制作会社は技術的な難易度を正確に把握し、現実的な非機能要件の提案が可能です。
3.評価基準と選定プロセス
提案の何を重視して評価するか(例: 価格、技術力、BtoB実績、コンテンツ戦略)と、選定スケジュール(プレゼン、質疑応答、決定)を明確に伝えます。これにより、制作会社はRFPの意図を正確に理解し、貴社のニーズに合致した提案を行うことができます。
非機能要件の定義を忘れがちな事例はありますか
Q. 要件定義で非機能要件が重要だと分かりました。特に忘れがちな非機能要件の具体例を教えてください。
A. BtoBサイトの要件定義で最も忘れられがちな非機能要件には、運用後の効率や安定性に関わる項目が多いです。
1.バックアップと復旧の要件
災害やシステム障害が発生した際、どの時点までのデータを、どれくらいの時間で復旧させるか(RTO/RPO)を具体的に定義すること。これが曖昧だと、最悪の場合、Webサイトが長期間停止し、営業機会を失うことになります。
2.ブラウザ/デバイスの対応範囲
一般的なブラウザだけでなく、貴社の顧客が使用する可能性のある古いOSや特定の業界で使われるデバイスでの表示・動作保証範囲を非機能要件として定義します。特に製造業では、現場のPC環境が古いことも想定されます。
3.コンテンツの多言語展開要件
将来的に海外展開や多言語対応を視野に入れる場合、CMSが多言語に構造的に対応できること、また多言語コンテンツの更新フローが煩雑にならないこと(運用面)を非機能要件に盛り込むべきです。後から多言語対応を追加しようとすると、大規模な改修が必要となるケースが多いです。
成功へのロードマップと行動
要点まとめ
BtoBサイトの要件定義の成功は、
●明確な「目的の知識」
●「戦略的な解決策」
そして「最新トレンドへの鮮度」を組み合わせることで実現します。
要件定義を終えたら、その文書を羅針盤として、パートナーと共に顧客体験の向上とビジネス成果の達成に向けて「行動」を起こすことが、成功への最終的な道筋です。
本記事を通じて、BtoBサイトの要件定義が、単なる機能リストの作成ではありません。
事業戦略に基づいたデジタル基盤構築の最重要フェーズであることがご理解いただけたかと思います。
本記事の情報を活用し、貴社のWebサイト構築プロジェクトを成功に導きましょう。
BtoBサイト要件定義成功へのロードマップ
1.認知・共感フェーズ
現状の課題と目的を明確化(KGI/KPI設定)。社内ステークホルダーとの合意形成と、プロジェクト体制を構築。
2.教育フェーズ
機能要件、非機能要件、コンテンツ要件を詳細に定義。CMS選定、MAツールとのシステム連携要件を固める。ペルソナとカスタマージャーニーマップを作成し、顧客体験を設計する。
3.刺激フェーズ
2025年最新トレンド(AI活用、Headless CMS、DX推進)を要件定義に組み込み、Webサイトの鮮度と拡張性を確保。RFPを作成し、BtoB特化の専門パートナーを選定。
4.行動フェーズ
要件定義書を承認・確定し、プロジェクトを構築フェーズへ移行。制作会社との連携を強化し、品質担保のためのテストへ積極的に参画。
成功への第一歩を踏み出す
要件定義は、Webサイトを「コスト」から「収益を生む資産」に変えるための最初にして最大の行動です。
曖昧な要望や、古くなった知識で要件定義を進めてしまうと、納品後に「こんなはずではなかった」という後悔に繋がりかねません。
特に製造業やIT企業といった専門性の高いBtoB領域では、事業理解と技術的な知見、そして最新のマーケティング知識を持った専門家の支援が不可欠です。
貴社の独自の強みや技術を最大限に活かしましょう。
商談獲得と売上向上に直結するWebサイト構築を実現するために、もし要件定義の進め方やパートナー選定、最新技術の組み込みにご不安があれば、ぜひ私たちアドミューズにご相談ください。
私たちは、BtoBサイト特化の専門知識と豊富なシステム連携実績に基づき、貴社の事業成功を第一に考えた、完璧な要件定義とWebサイト構築を伴走支援いたします。